「放射線技師」というお仕事に興味をお持ちで、もしかしたら「放射線技師 やめとけ」「放射線技師 後悔」なんて検索された方もいらっしゃるかもしれませんね。医療の現場で重要な役割を担う放射線技師ですが、一部では「やめとけ」と言われることもあるんです。なぜそう言われるのか、実際のところどうなのか、不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、放射線技師という職業の現実や、もし目指すのであれば知っておいてほしい「やめた方がいい」と言われる具体的な理由を8つ、詳しくお話ししていきます。これから進路を考える学生さんや、キャリアチェンジを検討されている社会人の方に、後悔のない選択をしていただくためのお役に立てたら嬉しいです。
この記事でお伝えしたいこと
- 放射線技師の仕事内容や必要な資質、活躍の場について知ることができます。
- 放射線技師が「やめとけ」と言われる具体的な8つの理由を理解できます。
- 放射線被ばくや精神的ストレス、給与、キャリアパスなどの懸念点が分かります。
- それでも放射線技師を目指す場合に、どのようにリスクを管理し、キャリアを築くかを知ることができます。
- 後悔しないための仕事選びに役立つ情報が得られます。
放射線技師という仕事の概要と求められる資質
まずはじめに、放射線技師というお仕事がどのようなものなのか、そしてどんな能力や心構えが求められるのか、基本のところからお話しさせてくださいね。この仕事を目指す上で、まずはその全体像をしっかりと把握することが大切なんですよ。
放射線技師とは?仕事内容の基本
放射線技師は、医療現場で放射線を使って病気の診断や治療をサポートする専門職です。主に、レントゲン撮影やCT、MRIといった画像診断装置の操作を担当するイメージが強いかもしれませんね。でも、実はそれだけではない、多岐にわたるお仕事があるんですよ。
具体的には、次のような業務を担当しています。
- X線撮影(レントゲン): 骨折や肺炎など、体の内部を画像化して診断に役立てます。
- CT(コンピューター断層撮影): 体の輪切り画像を撮影し、より詳細な情報を得て病変の特定に貢献します。
- MRI(磁気共鳴画像診断): 磁気と電波を使って、脳や脊髄、関節などの軟部組織を鮮明に画像化します。放射線を使わないため、被ばくの心配がないのが特徴ですね。
- 核医学検査: 放射性医薬品を体内に投与し、その薬が集まる様子を画像化して臓器の機能や病気の進行度を調べます。
- 放射線治療: がんなどの病気に対して、放射線を照射して治療を行います。非常に専門的な知識と精密な技術が求められる分野なんです。
- 超音波検査(エコー): 放射線技師が超音波検査を担当することもあります。お腹の中の臓器や血管の状態などをリアルタイムで観察できる検査ですね。
これらの検査や治療を行う際には、患者さんの状態を正確に把握し、適切な位置に誘導して、安全に配慮しながら装置を操作することが求められます。診断や治療に直結する重要な役割なので、一つ一つの作業に集中力と正確性が欠かせません。
医療の進歩とともに、放射線技師の役割も広がっているんですよ。最新の医療機器の操作はもちろん、患者さんのデータ管理や、ときには医師への情報提供、さらには放射線防護の専門家としての役割も期待されています。
放射線技師に求められる資質と適性
放射線技師として活躍するためには、いくつかの大切な資質や適性が必要になってきます。技術的なスキルはもちろんですが、それ以上に人間的な部分が大きく影響することも多いんですよ。
例えば、以下のような資質が挙げられます。
- 高い専門知識と技術: 放射線に関する物理学や生物学、解剖学、病理学など、幅広い知識が必須です。また、精密な機器を操作する技術や、安全管理に関する知識も欠かせません。
- 注意力と集中力: 検査や治療はミリ単位の精度が求められることもあります。小さなミスが診断や治療に大きな影響を与えることもあるため、常に細心の注意を払い、集中して業務に取り組む力が必要です。
- コミュニケーション能力: 患者さんは不安を抱えていることが多いですよね。安心して検査を受けてもらえるよう、優しく丁寧に説明し、信頼関係を築くコミュニケーション能力が大切なんです。また、医師や看護師、他の医療スタッフとの連携もスムーズに行う必要があります。
- 冷静な判断力と危機管理能力: 緊急性の高い患者さんへの対応や、予期せぬトラブルが発生した際にも、落ち着いて状況を判断し、適切に対処する能力が求められます。放射線の安全管理においても、常にリスクを考慮し、適切に対応する危機管理能力が重要です。
- 倫理観と責任感: 患者さんの個人情報や身体に関する情報を扱うため、高い倫理観が求められます。また、放射線という特殊なものを取り扱う責任の重さを常に認識し、プロフェッショナルとしての自覚を持つことが大切です。
これらの資質は、日々の業務を通じて磨かれていくものですが、元々持っていると、よりスムーズに仕事に慣れることができるかもしれませんね。特に、患者さんとの向き合い方は、医療従事者として非常に重要なポイントだと思いますよ。
放射線技師の活躍の場と将来性
放射線技師が活躍できる場所は、病院だけではありません。実に様々な場所で、その専門性が求められているんですよ。
主な活躍の場は、次の通りです。
- 総合病院・大学病院: 最も一般的な勤務先で、様々な症例や最新の機器に触れる機会が多いです。
- クリニック・診療所: 地域密着型で、患者さんとの距離が近いのが特徴です。X線撮影やCT検査が中心となることが多いですね。
- 健診センター: 病気の早期発見を目的とした健康診断や人間ドックで、X線撮影やCT、マンモグラフィなどの検査を担当します。
- 医療機器メーカー: 放射線診断装置や治療装置の開発、販売、技術サポートに携わることもあります。自分の専門知識を活かして、新しい医療技術の発展に貢献できるやりがいのある分野です。
- 研究機関: 放射線医学に関する研究や、新しい画像診断技術の開発に携わることも可能です。

将来性については、高齢化社会の進展とともに、医療の需要は今後も高まることが予想されます。特に、病気の早期発見や精密な診断の重要性が増している中で、放射線技師の役割はますます大きくなるでしょう。
AI(人工知能)の導入による業務の変化も考えられますが、それはあくまで診断をサポートするツールであり、患者さんとの直接のコミュニケーションや機器の細かな調整、緊急時の判断など、人間の専門性が求められる部分は残ると言われています。むしろ、AIと連携することで、より高度で効率的な医療を提供できるようになる可能性も秘めているんですよ。
2020年の経済産業省の調査でも、医療・ヘルスケア分野におけるAIの活用は、今後さらに進むと予測されています。しかし、放射線技師のような専門職は、技術を使いこなす側として、新しい時代に対応していく力が求められるでしょう。
放射線技師を「やめとけ」と言われる8つの深刻な理由
さて、ここからが本題です。放射線技師という魅力的なお仕事でありながら、なぜ「やめとけ」と言われることがあるのでしょうか。私がリサーチした結果、多くの現役技師さんや、この道を目指そうとして挫折した方々から、共通するいくつかの「しんどい」ポイントや「後悔」の声が聞かれました。これからその8つの理由を、一つずつ丁寧にお話ししていきますね。
【理由①】見えない放射線への不安と健康リスク
放射線技師と聞いて、まず頭に浮かぶのが「放射線」ではないでしょうか。放射線は目に見えないものですから、その影響について不安を感じるのは当然のことですよね。現役の放射線技師さんの中にも、やはりこの点について懸念を抱いている方は少なくないようです。
「日々の業務で放射線を扱う以上、どれだけ防護していても『本当に安全なのかな?』という不安が常に付きまといます。特に若いうちはあまり気にならないかもしれませんが、将来を考えると心配になることもありますね。」
もちろん、医療現場では放射線技師の被ばく線量を厳しく管理し、防護のための対策も徹底されています。鉛入りのエプロンや防護板の使用、線量計による個人被ばく線量の測定など、安全管理のルールが厳格に定められているんです。日本の放射線防護の基準は世界的に見ても非常に高いレベルにあると言われていますよ。
しかし、それでも「見えない」という特性からくる心理的な不安は、なかなか拭い去れるものではありません。特に、妊娠を考えている女性技師の方にとっては、より深刻な悩みとなる場合もありますね。国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告でも、医療従事者の被ばく線量限度は一般公衆よりも高く設定されていますが、それでも個人の不安は別問題なんです。
放射線業務に従事する上で、健康管理は非常に重要です。定期的な健康診断や被ばく線量のチェックは必須ですが、それでも「万が一」を考えてしまうのは、人間として自然な感情ですよね。
【理由②】精神的ストレスと患者対応の難しさ
医療現場は、患者さんの命に関わる非常に緊張感のある場所です。放射線技師も例外ではありません。精神的なストレスを感じやすい要因がたくさんあるんです。
- 患者さんの不安や苦痛への対応: 検査を受ける患者さんは、病気への不安や、慣れない検査で身体的な苦痛を感じていることがあります。そのような患者さんの気持ちに寄り添い、安心させながら検査を進めるのは、精神的に大きな負担となることがあります。特に、小児や高齢者、認知症の患者さんなど、コミュニケーションが難しいケースでは、より細やかな配慮と忍耐が求められますね。
- 緊急対応のプレッシャー: 救急患者や重症患者の検査では、一刻を争う状況の中で迅速かつ正確な判断が求められます。些細なミスも許されないため、常に高いプレッシャーを感じながら業務にあたることになります。
- 感情労働の側面: 患者さんの感情を受け止め、自分の感情をコントロールしながら対応する「感情労働」の側面が強いのも、精神的ストレスの一因となるでしょう。

実際に、ある現役の放射線技師さんからはこんな声も聞かれました。
「患者さんの中には、検査への理解が得られず、パニックになってしまう方もいらっしゃいます。そういったときに、どうすれば安全に、そしてスムーズに検査を進められるか、その都度ベストな方法を考えなければなりません。精神的に消耗することもありますね。」
もちろん、患者さんから感謝の言葉をいただけた時には大きな喜びを感じることもできます。しかし、日々の業務の中で抱える精神的な負担は、この仕事を続けていく上で無視できない課題の一つだと言えるでしょう。
【理由③】給与水準とキャリアアップの限界
安定した専門職というイメージがある放射線技師ですが、給与水準やキャリアアップの面で、期待と現実のギャップを感じる方もいらっしゃるようです。
日本の平均給与と比較すると、放射線技師の給与は決して低いわけではありませんが、医療系の他の職種、例えば医師や一部の看護師と比較すると、伸び悩む傾向にあると言われています。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」などを見ると、経験年数や役職によって差はありますが、大幅な年収アップは難しいと感じる方が多いようです。
キャリアアップについても、病院内での役職は限られています。
- 主任技師
- 技師長
といった管理職への昇進はありますが、そのポストの数は多くありません。専門性を高めて認定資格を取得したり、大学院に進学して研究職を目指す道もありますが、これも誰もができる選択肢ではないですよね。
キャリアパスの多様性という点では、メーカーへの転職や研究機関への移行も可能ですが、これも狭き門です。一般企業のように、部署異動で全く違う経験を積む、といったフレキシブルなキャリアチェンジは、この業界ではあまり期待できないかもしれません。
特定の専門分野を深く掘り下げていくことはできますが、仕事内容そのものの大きな変化や、それに伴う大幅な給与アップを望む方にとっては、物足りなさを感じる可能性もあるでしょう。
【理由④】技術進歩と学習の継続的なプレッシャー
医療技術の進歩は本当に目覚ましいですよね。特に画像診断の分野は、新しい機器や検査方法が次々と登場しています。これは喜ばしいことである反面、放射線技師にとっては、常に学び続けなければならないというプレッシャーにもなるんです。
- 新しい医療機器の導入: 最新のCTやMRI、PET装置など、高機能な機器が開発されるたびに、その操作方法や原理、画像評価のポイントなどを習得する必要があります。
- 新しい診断技術や治療法の出現: 例えば、AIを活用した画像解析や、より精密な放射線治療計画など、日進月歩で知識をアップデートしていくことが求められます。
- 認定資格の取得: 専門性を高めるためには、マンモグラフィ認定技師やCT認定技師など、様々な認定資格を取得することが推奨されます。これには、自己学習や研修への参加が不可欠です。
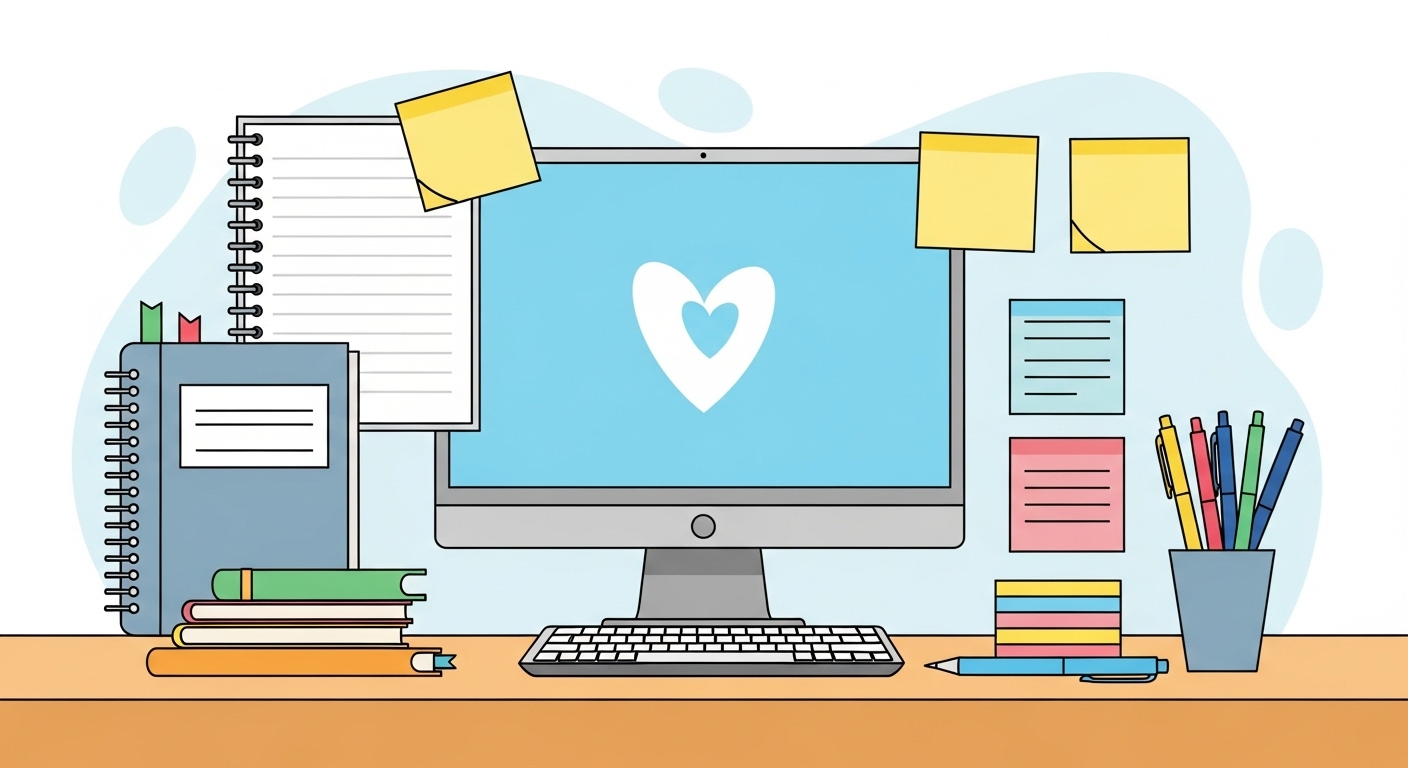
仕事が終わってからの勉強や、休日を使っての学会参加なども珍しくありません。
「学生時代に学んだ知識だけでは、すぐに時代遅れになってしまいます。常に新しい情報をキャッチアップし、技術を磨き続ける必要があるので、正直なところ、プライベートな時間も削って勉強していることが多いですね。」
このように、専門職として常に最新の知識と技術を身につけていく向上心は素晴らしいことですが、そのための学習負荷が非常に大きいという点は、覚悟しておくべき現実なんです。
【理由⑤】夜勤・オンコールなど不規則な勤務体制
病院勤務の放射線技師は、24時間体制の医療を支えるため、不規則な勤務になりがちです。夜勤やオンコール(緊急時に病院に駆けつける待機業務)は、この仕事の避けられない側面と言えるでしょう。
- 夜勤: 救急患者への対応や、日中にできない検査を行うために夜勤があります。夜勤明けは疲労が蓄積しやすく、生活リズムが乱れることで体調を崩してしまう方もいらっしゃいます。
- オンコール: 自宅で待機し、緊急時にはすぐに病院へ向かう必要があるため、プライベートな予定が立てにくいという声もよく聞かれます。せっかくの休日も、常に「いつ呼び出されるか」という緊張感から解放されないことがあるんです。

特に総合病院や大学病院など、救急医療を担う大きな施設ほど、この傾向は顕著になります。
「夜勤明けは、とにかく体がだるくて、家族との時間もなかなか取れません。友人と出かける約束をしていても、オンコールが入るかもしれないと思うと、遠出するのもためらってしまいます。」
若いうちは体力で乗り切れても、年齢を重ねるごとに身体的な負担が増していく可能性もあります。ワークライフバランスを重視する方にとっては、この不規則な勤務体制は非常に大きな障壁となるかもしれませんね。
【理由⑥】専門性の高さゆえの転職・キャリアパスの限定性
放射線技師は、非常に高い専門性を持つ職業です。しかし、その専門性が高すぎるがゆえに、一度この道に進むと、他の分野への転職やキャリアチェンジが難しくなるという側面もあります。
放射線技師の資格は、医療現場での放射線業務に特化したものです。そのため、全く異なる業界や職種への転職を考えた場合、これまでの専門知識やスキルが直接的に活かせる場面が少ないと感じてしまうことがあります。
例えば、一般企業での営業職や事務職などに転職しようと思っても、放射線技師として培った経験が必ずしも有利に働くとは限りません。一から新しいスキルを身につけなければならないため、転職活動が難航したり、年収が下がってしまうケースも考えられます。
一度放射線技師になると、その専門性を活かす場は医療機関や医療機器メーカーなどに限られる傾向があります。これが、もし将来的に「やっぱり違う仕事がしたい」と思ったときに、選択肢が狭まってしまうというデメリットにもなり得るんです。
【理由⑦】人間関係の複雑さとチームワークの重要性
医療現場は、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、そして放射線技師といった、様々な専門職が集まって働く場所です。患者さんの治療を進めるためには、それぞれの職種が連携し、円滑なコミュニケーションを取ることが非常に重要になってきます。
しかし、様々な専門性や価値観を持つ人が集まる環境だからこそ、人間関係が複雑になることもあります。
- 部署内の人間関係: 同じ放射線科の中でも、先輩・後輩の関係や、それぞれの得意分野の違いから、意見の食い違いが生じることもあります。
- 他部署との連携: 医師からの指示、看護師からの情報共有など、他職種とのコミュニケーションが円滑でないと、業務に支障が出たり、時には患者さんに影響を及ぼしてしまう可能性もあります。
- チームワークのプレッシャー: 個人の能力だけでなく、チームとして機能することが求められます。もしチーム内の人間関係がうまくいかないと、仕事の効率が落ちるだけでなく、精神的なストレスも大きくなってしまいます。

ある技師さんは、こんな風に話していました。
「チームで動くことが多いので、どうしても人間関係は大切です。気が合わない人がいると、毎日仕事に行くのが辛くなることもあります。報告・連絡・相談がしっかりできないと、医療ミスにも繋がりかねないので、コミュニケーションは常に気を遣いますね。」
どんな職場でも人間関係は大切ですが、命を預かる医療現場では、それがより強く求められ、時にはプレッシャーとなることもあるのですね。
【理由⑧】医療事故リスクと責任の重さ
放射線技師の仕事は、患者さんの診断や治療に直結するため、その責任は非常に重いです。特に、医療事故が発生した場合のリスクは、この仕事の最もシビアな側面と言えるでしょう。
- 検査ミスや誤診への影響: 撮影の仕方を誤ったり、適切な画像が提供できなかったりすると、誤診につながる可能性があります。その結果、患者さんの治療が遅れたり、不適切な治療が行われたりすることもあり得ます。
- 放射線被ばくの管理責任: 患者さんに適切な線量で放射線を照射する責任があります。過剰な被ばくは患者さんの健康を害する可能性があるため、常に細心の注意を払い、設定を厳しくチェックしなければなりません。
- 法的・倫理的責任: 医療事故が発生した場合、個人としての責任はもちろん、組織としての責任も問われることになります。心理的な負担は計り知れません。
実際に、患者さんに万が一のことがあった場合、医療従事者は深い自責の念に駆られることになります。それは、単なる「失敗」では済まされない、人の命に関わることだからです。
毎日、多くの患者さんの検査を行う中で、常に完璧な状態で業務をこなすのは並大抵のことではありません。しかし、その「完璧」が求められるのが医療現場の現実なんです。この重い責任に耐えうる精神力が必要とされますが、それがプレッシャーとなり、この仕事から離れることを考える方もいると聞きますよ。
それでも放射線技師を目指すなら知っておくべきこと
ここまで、放射線技師の仕事には「やめとけ」と言われるような大変な側面があることをお話ししてきました。でも、それでもなお放射線技師という仕事に魅力を感じ、目指したいという気持ちがある方もいらっしゃるかもしれませんね。その強い思いを応援したいからこそ、私がさらに知っておいてほしいことをお伝えします。大変な面を理解した上で、どうすればそのリスクを管理し、充実したキャリアを築けるかについて考えていきましょう。
健康リスクを最小限に抑えるための対策
放射線被ばくへの不安は、放射線技師を目指す上で最も気になる点の一つですよね。でも、医療現場では、このリスクを最小限に抑えるための様々な対策が講じられているんです。
- 厳格な防護体制: 鉛入りのエプロンや防護メガネ、甲状腺プロテクターなど、個人の防護具は必ず着用します。また、検査室の壁には放射線を遮蔽する鉛が埋め込まれているなど、施設の防護体制も徹底されています。
- 線量計による個人被ばく線量の管理: 全ての放射線技師は、バッジ型の線量計を装着し、定期的に被ばく線量を測定・管理されています。これは法律で義務付けられているんですよ。もし規定値を超えそうになった場合は、業務内容の見直しや、一時的な異動などの対策が取られます。
- 定期的な健康診断: 放射線業務に従事する人は、年に1回以上の健康診断が義務付けられています。血液検査など、放射線の影響がないかをチェックする項目も含まれているんです。
「放射線業務従事者に対する電離放射線健康診断の手引き」など、国が定めるガイドラインに沿って厳密に管理されていますので、過度に心配しすぎる必要はないとされています。しかし、ご自身で積極的に知識を学び、安全意識を高く持つことが、何よりも大切なんです。
精神的負担を軽減するための心構えと対処法
患者さん対応の難しさや緊急対応のプレッシャーなど、精神的なストレスが多い放射線技師の仕事。でも、この負担を軽減し、前向きに仕事に取り組むための心構えや対処法はたくさんありますよ。
- コミュニケーションスキルの向上: 患者さんの不安を取り除くためには、一方的に話すのではなく、相手の気持ちに寄り添い、共感する姿勢が大切です。傾聴の姿勢を心がけ、検査の流れを分かりやすく説明することで、患者さんの協力も得やすくなります。
- ストレスマネジメント: 趣味や運動など、仕事から離れてリフレッシュできる時間を持つことが重要です。同僚や信頼できる人に相談したり、専門機関のサポートを利用したりするのも良い方法です。
- チームでの協力体制の構築: どんなに大変な状況でも、一人で抱え込まず、周りの同僚や先輩に助けを求める勇気を持つことが大切です。チーム全体で情報を共有し、協力し合うことで、個人の負担を減らすことができます。
自分一人で完璧を目指すのではなく、チームとして最善を尽くすという考え方にシフトすることが、精神的な負担を減らす鍵になるはずです。
キャリアパスを広げるための戦略
放射線技師のキャリアパスは限定的だ、というお話をしましたが、それでも工夫次第で選択肢を広げることは可能です。
- 専門分野の認定資格取得: マンモグラフィ認定技師、CT認定技師、磁気共鳴専門技術者など、特定の専門分野の認定資格を取得することで、その分野のエキスパートとしての価値を高めることができます。これにより、より専門性の高い医療機関での勤務や、管理職への昇進の道が開ける可能性があります。
- 他職種連携・管理能力の習得: 将来的に管理職を目指すのであれば、チームをまとめるリーダーシップや、他部署との連携を円滑にするための調整能力を磨くことが大切です。
- 医療機器メーカーやCROへの転職: 臨床現場での経験を活かし、医療機器メーカーのアプリケーションスペシャリスト(製品の専門知識を活かして、医師や技師に使い方を指導したり、トラブルシューティングを行ったりする職種)や、治験施設支援機関(CRO)で臨床開発に携わる道もあります。
- 大学院進学・研究活動: より深く放射線医学や画像診断について学びたい場合は、大学院に進学し、研究者としてのキャリアを築くことも可能です。
常にアンテナを張り、新しい情報や技術を積極的に学ぶ姿勢が、キャリアの幅を広げることに繋がりますよ。
ワークライフバランスを考慮した働き方
不規則な勤務体制は放射線技師の大きな課題ですが、働く場所や働き方を選ぶことで、ワークライフバランスを改善できる可能性もあります。
- 勤務先の選択: 救急医療を担う総合病院では夜勤やオンコールが多い傾向にありますが、健診センターやクリニックでは、日勤のみの勤務体制が一般的です。ワークライフバランスを重視したい場合は、このような施設を選ぶのも一つの方法です。
- 時短勤務や育児休暇制度の活用: 女性の場合は、結婚や出産を機に、時短勤務制度や育児休暇制度が充実している職場を選ぶことが重要です。長く仕事を続けるためには、ライフステージの変化に対応できる柔軟な働き方ができる職場を見つけることが大切です。
- 趣味やリフレッシュの時間の確保: どんなに忙しくても、意識的に自分のための時間を作るようにしましょう。心身のリフレッシュは、仕事のパフォーマンスを維持するためにも不可欠です。

求人情報を確認する際には、給与だけでなく、勤務時間や休暇制度、福利厚生など、働き方に関する情報もしっかりとチェックするようにしてくださいね。
放射線技師を「やめとけ」と言われる理由の総括
ここまで、放射線技師というお仕事の魅力とともに、なぜ「やめとけ」と言われるのか、その具体的な理由を8つ、そしてそれでも目指すならどうすべきかをお話ししてきました。最後に、今回の内容をもう一度、簡潔にまとめさせていただきますね。
放射線技師を「やめとけ」と言われる主な理由
- 見えない放射線への不安と健康リスク: 厳重な管理下にあるものの、心理的な不安はゼロにはなりません。
- 精神的ストレスと患者対応の難しさ: 患者さんの不安や緊急対応、感情労働による精神的負担があります。
- 給与水準とキャリアアップの限界: 他の医療職と比べ給与の伸び悩みが指摘され、管理職ポストも限られています。
- 技術進歩と学習の継続的なプレッシャー: 最新技術に対応するため、生涯にわたる学習が不可欠です。
- 夜勤・オンコールなど不規則な勤務体制: 24時間体制の医療現場では、生活リズムが不規則になりがちです。
- 専門性の高さゆえの転職・キャリアパスの限定性: 専門性が高い分、他の分野へのキャリアチェンジが難しい側面があります。
- 人間関係の複雑さとチームワークの重要性: 多職種連携が必須であり、人間関係が複雑になることもあります。
- 医療事故リスクと責任の重さ: 患者さんの命に関わる責任は非常に大きく、精神的なプレッシャーとなります。
放射線技師というお仕事は、病気の診断や治療に不可欠な、社会貢献性の高い、とてもやりがいのある職業です。多くの患者さんの回復を間近で見ることができ、感謝されることも多いでしょう。その一方で、専門職ならではの厳しい側面や、精神的・身体的な負担があることも事実なんです。
今回の記事で挙げた「やめとけ」と言われる理由をしっかりと理解した上で、ご自身の適性や価値観、そして将来の目標と照らし合わせてみてくださいね。どのような仕事にも良い面と大変な面がありますが、大切なのは、その両方をきちんと知った上で、ご自身が納得できる選択をすることです。
この記事が、皆さんのキャリア選択の一助となれば嬉しいです。



