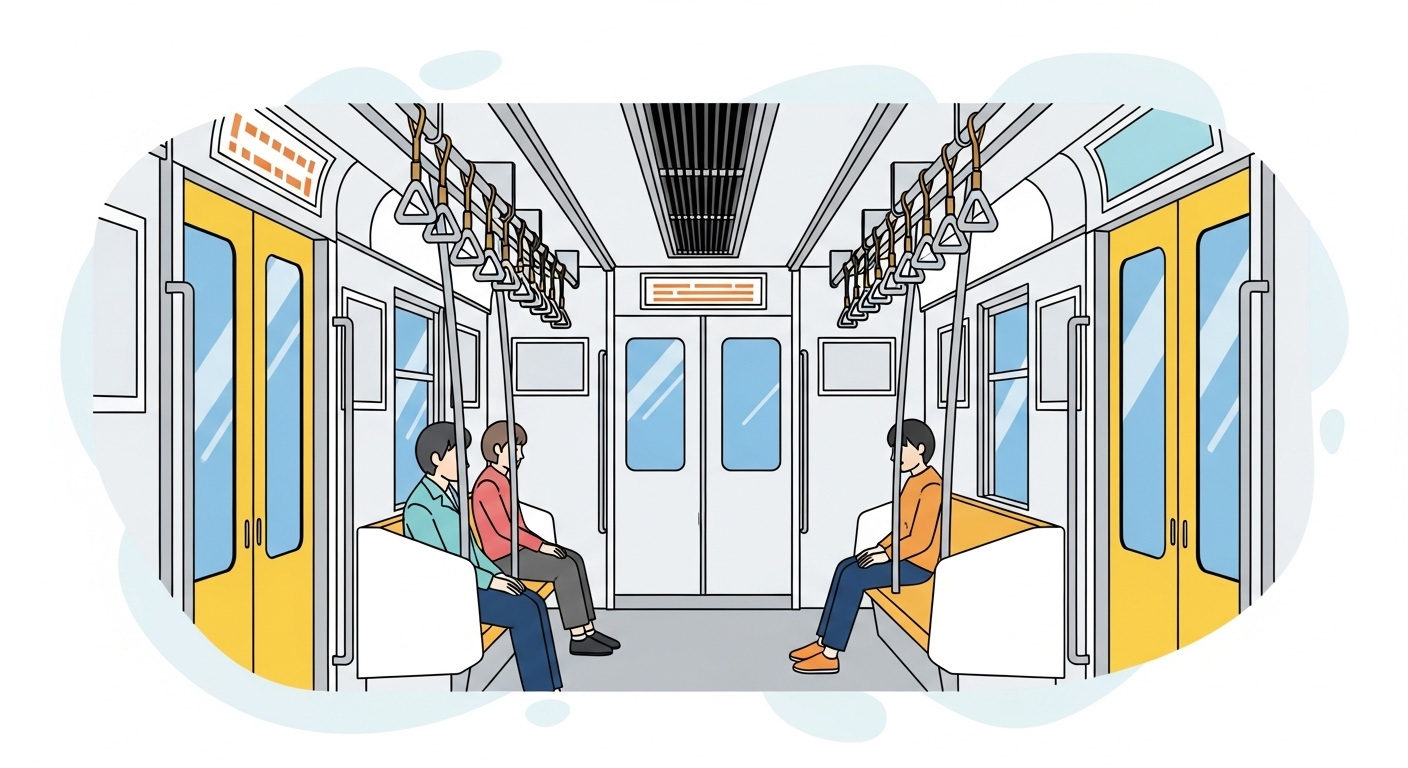「年間休日105日」という数字を聞いて、皆さんはどのように感じますか?
もしかしたら、「週休2日じゃないの?」とか、「祝日は休めるのかな?」といった疑問が頭をよぎるかもしれませんね。最近では年間休日120日以上が一般的な企業も増えてきた中で、なぜ105日という数字が「やめとけ」「後悔する」といったネガティブな言葉と結びつけられることがあるのでしょうか?
確かに、休日が少ないと聞くと、少し不安になりますよね。ですが、本当に年間休日105日の会社は避けるべきなのでしょうか?
このブログでは、年間休日105日の実態から、皆さんが知っておくべき思わぬ落とし穴、そして、もし年間休日105日の会社を選ぶ場合に後悔しないための大切なポイントまで、私の視点から丁寧にお伝えしたいと思います。ぜひ、ご自身の働き方を考える上での参考にしてみてくださいね。
この記事でお伝えしたいこと
- 年間休日105日の具体的な意味と、労働基準法との関連
- 年間休日105日で後悔や失敗を招きやすい7つの具体的な理由
- それでも年間休日105日の会社を選ぶ際に、知っておくべき注意点
- 年間休日105日でも満足して働ける人の特徴と、働き方の工夫
年間休日105日の実態とは?法律との関係を解説
まずは、「年間休日105日」が具体的にどのような状態を指すのか、そして法律上は問題ないのかについて、詳しく見ていきましょう。この数字の持つ意味を正しく理解することが、その後の判断においてとても大切になるんです。
年間休日105日は「週休2日」ではない?
「週休2日制」という言葉はよく聞きますが、実は年間休日105日は「完全週休2日制」とは異なることが多いんです。多くの方が想像する「毎週土日がお休み」というわけではないのが実情なんですよ。
年間休日105日とは、ざっくり言うと、
- 月に約1.5回は土曜出勤がある
- 祝日は基本出勤となる
というケースがほとんどです。
例えば、土日・祝日が完全に休みである会社の場合、年間休日はおよそ120日以上になります。内訳としては、
- 土曜日:52日
- 日曜日:52日
- 祝日:年間約16日
- 年末年始や夏季休暇:数日
これらを合計すると、120日を超えるのが一般的です。
それに対して年間休日が105日ということは、この120日よりも15日以上も少ない計算になりますよね。その不足分は、主に「祝日が出勤日となる」「毎月どこかの土曜日が出勤日となる」ことで埋められていることが多いんです。
つまり、カレンダー通りのお休みを期待して入社すると、「あれ?こんなに休みが少ないの?」とギャップを感じてしまう可能性が高いんです。特に、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などの大型連休が短かったり、そもそもなかったりするケースも珍しくありません。
そのため、「週休2日制」と書かれていても、「年間休日105日」であれば、それは「毎週2日休めるわけではない」と認識しておくことが、後悔しないための第一歩ですよ。
労働基準法の最低ラインと年間休日105日
では、年間休日105日は、日本の法律である「労働基準法」に照らし合わせて問題ないのでしょうか?この点は、とても大切なポイントですよね。
労働基準法では、労働時間の上限が定められています。
具体的には、
- 1週間に40時間
- 1日に8時間
を原則として超えて労働させてはならない、と定められています。
そして、休日については、「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定されています。これを「法定休日」と呼びます。1週間に1日の休日ですから、1年間(52週)で考えると、最低でも52日の休日が必要ということになりますね。
では、年間休日105日はどうでしょうか?
105日というのは、この法定休日の52日を大きく上回っていますよね。そのため、年間休日105日という設定自体は、労働基準法に違反するものではありません。
しかし、これには条件があります。労働基準法で定められた週40時間労働の原則を守りつつ、年間105日の休日を確保するためには、どのような働き方になるのでしょうか?
| 項目 | 一般的なケース(年間休日120日) | 年間休日105日のケース |
|---|---|---|
| 1日の労働時間 | 8時間 | 8時間 |
| 年間所定労働時間 | 約1920時間(週40時間×52週) | 約2040時間(週40時間×52週 + 不足分) |
| 年間労働日数 | 約240日 | 約250日 |
年間休日105日で週40時間労働を維持するためには、1日の労働時間を短縮するか、特定期間の変形労働時間制などを導入する必要があります。多くの場合、1日の労働時間は8時間のままで、休みを減らすことで労働日数を増やしているため、実質的に週40時間を超える労働を強いられている可能性も出てくるんです。これは注意が必要ですね。
法律上問題がないからといって、それが「良い働き方」であるとは限りません。ご自身の健康やプライベートを考えたときに、年間休日105日という働き方が本当に合っているのか、慎重に考える必要があるんです。
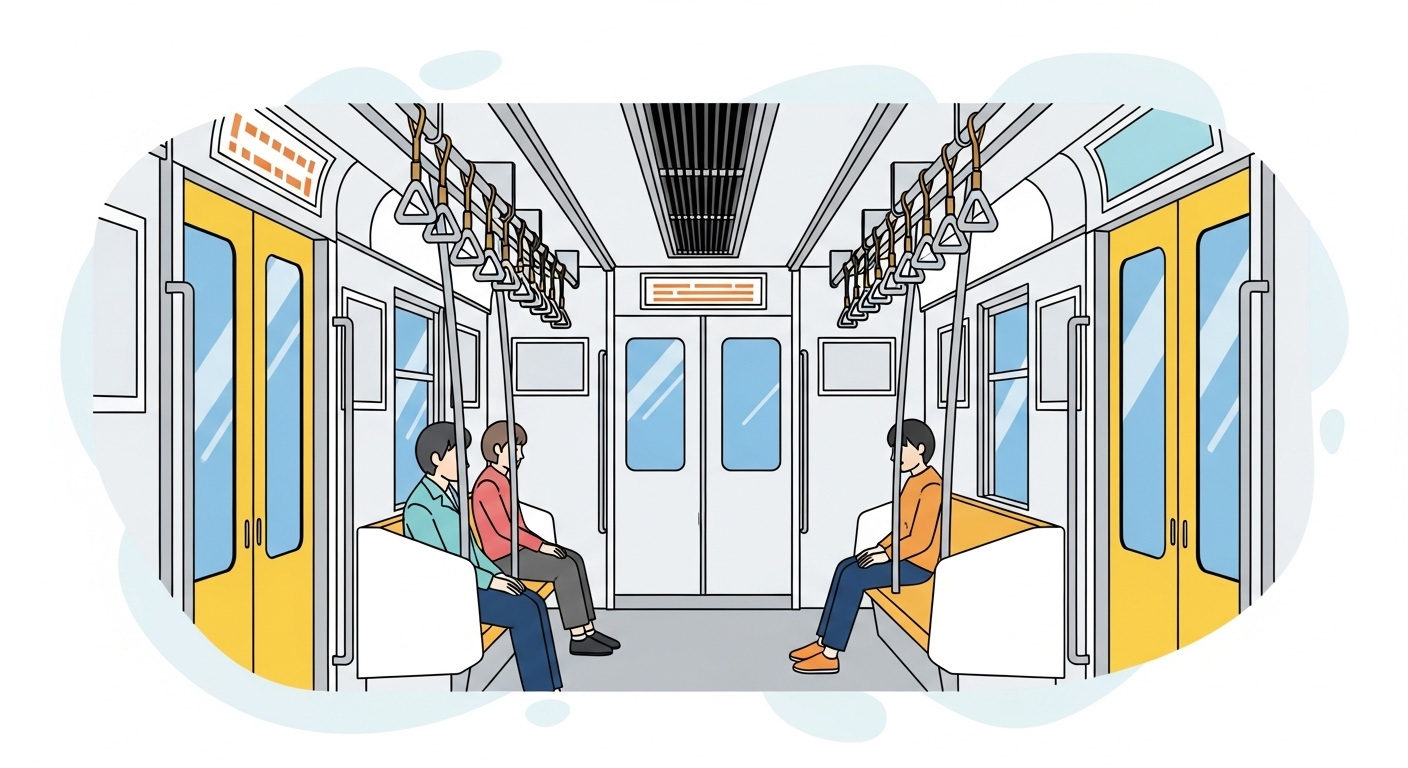
一般的な年間休日数との比較
近年、多くの企業では、従業員のワークライフバランスを重視する傾向が強まり、年間休日数を増やす動きが見られます。では、年間休日105日は、世間一般的にどのくらいの水準なのでしょうか?
厚生労働省の「就労条件総合調査」などによると、企業が年間で与える平均的な休日数は、おおむね120日程度と言われています。これは、ほとんどの企業で土日・祝日が休みとなる「完全週休2日制」が導入されていることを示唆していますね。
具体的な内訳は、先ほどもお伝えしたように、
- 土曜日:約52日
- 日曜日:約52日
- 祝日:約16日
- 年末年始休暇、夏季休暇など:数日
合計で120日を超えているのが一般的です。
この平均値と比較すると、年間休日105日は、明らかに少ない数字であることがわかりますよね。年間で15日以上も休みが少ないということは、月に換算すると1日〜2日程度休みが少ないということになりますが、この数日の差が、皆さんの生活に大きな影響を与える可能性があるんです。
特に、友人や知人が年間休日120日以上の企業に勤めている場合、大型連休の過ごし方や、家族との時間、趣味の時間などに大きな差が生まれてしまう可能性があります。それが積もり積もって、「自分だけ休みが少ない…」と感じてしまうこともあるかもしれません。
なぜ、年間休日105日という企業が存在するのでしょうか?
- サービス業や製造業など、土日祝日の稼働が必要な業種
- 人手不足で、どうしても休日を減らさざるを得ない中小企業
- コスト削減のため、人件費の一部として休日を減らしている企業
といった理由が考えられます。
もちろん、企業の事情は様々ですが、求人情報で「年間休日105日」と記載されていた場合、まずは「一般的な水準よりも休みが少ない」という認識を持つことが大切です。そして、その少ない休日の中で、ご自身がどのように働くことになるのかを具体的にイメージしてみるようにしてくださいね。
年間休日105日は本当にやめとけ?失敗と後悔を避けるべき理由7選
さて、ここからは、なぜ年間休日105日の会社を選ぶべきではない、あるいは慎重になるべきなのかについて、具体的な7つの視点から詳しくお話ししていきたいと思います。皆さんが後悔しないために、ぜひ知っておいてほしいことばかりなんですよ。
【理由①】十分な休息が取れず、健康を損なう可能性が高い
年間休日105日の会社で働くことの最も大きな懸念点は、「十分な休息が取れず、心身の健康を損なう可能性が高い」ということです。
一般的な年間休日120日の会社と比べると、年間で15日以上も休みが少ないということは、単純に労働日数が多くなるということですよね。月に換算すると、毎週のように土日連休が取れるわけではなく、月に1〜2回は土曜出勤があるようなイメージです。
休みが少ないと、このような問題が起こりやすくなります。
- 疲労の蓄積:休日にしっかり休めないと、肉体的な疲労が抜けきらず、常にだるさや倦怠感を感じるようになります。
- 集中力の低下:疲労が蓄積すると、仕事中の集中力や判断力が低下し、ミスをしやすくなったり、業務効率が落ちたりする可能性があります。
- 精神的な不調:オンオフの切り替えがうまくいかず、常に仕事のプレッシャーを感じることで、ストレスが溜まりやすくなります。不眠や気分の落ち込みなど、精神的な不調につながることもあります。
- 体調不良の増加:免疫力が低下し、風邪をひきやすくなったり、生活習慣病のリスクが高まったりすることもあります。
「年間休日105日の会社で働いていましたが、体が常にだるくて、週末はただ寝るだけで終わっていました。趣味の時間も取れず、次第に会社に行くのが辛くなり、結局体調を崩して退職することに…。」
このような声からもわかるように、休息不足は、皆さんの心と体に深刻な影響を及ぼしかねません。若いうちは乗り切れても、年齢を重ねるにつれて、その影響はより顕著になってくるでしょう。ご自身の健康は、何よりも大切な資本です。十分な休息が確保できない環境で働き続けることは、長期的に見て大きなリスクとなることを理解しておく必要がありますね。

【理由②】プライベートな時間が極端に少なくなる
私たちの生活は、仕事だけで成り立っているわけではありませんよね。趣味を楽しんだり、家族や友人と過ごしたり、自己啓発に時間を費やしたりと、プライベートな時間も人生を豊かにするために欠かせない要素です。しかし、年間休日105日の会社では、このプライベートな時間が極端に少なくなる可能性が高いんです。
年間休日105日で特に影響が出やすいのは、次のような点です。
- 趣味や習い事:平日は仕事で疲れてしまい、休日も不定期となると、計画的に趣味や習い事に取り組むのが難しくなります。
- 家族や友人との時間:土日・祝日がすべて休みではないため、家族との予定が合わせにくかったり、友人と旅行に行く機会が減ったりするかもしれません。特に、周囲の友人がカレンダー通りの休みを取っている場合、疎外感を感じることもあるでしょう。
- 自己投資やスキルアップ:仕事以外の時間で資格の勉強をしたり、新しいスキルを学んだりしたいと思っても、時間的・精神的な余裕がなく、なかなか実現できない可能性があります。
- 家事や育児:共働き世帯の場合、家事や育児の分担が難しくなったり、負担が増えたりすることが考えられます。
「友人と予定を合わせるのが本当に大変でした。みんながゴールデンウィークや年末年始に旅行に行っているのに、自分だけ仕事…。疎外感を感じて、だんだん誘われることも減っていきました。」
このような経験談からもわかるように、プライベートの時間が不足することは、精神的な充実感を奪い、生活の質を低下させてしまうことにつながります。仕事は大切ですが、人生全体のバランスを考えたときに、プライベートな時間を犠牲にしすぎることが、後々の後悔につながる可能性は高いでしょう。
【理由③】ワークライフバランスが崩壊しやすい
先ほどの「休息不足」や「プライベート時間の減少」にも関連しますが、年間休日105日という環境は、「ワークライフバランス」を保つことを非常に困難にさせます。
ワークライフバランスとは、仕事と私生活の調和を意味します。仕事にやりがいを感じつつも、プライベートも充実させることで、心身ともに健康で豊かな生活を送ることを目指す考え方ですよね。
年間休日105日だと、なぜワークライフバランスが崩れやすいのでしょうか?
- 強制的な「仕事モード」の継続:休みが少ないことで、脳が常に仕事モードから抜け出せず、リフレッシュする機会が失われます。
- 疲労回復の遅れ:休みが少ないため、心身の疲労が十分に回復せず、仕事のパフォーマンスにも悪影響が出やすくなります。
- 生活の質の低下:趣味や大切な人との時間が減ることで、生活全体の満足度が低下し、仕事への意欲も失われがちになります。
- ストレスの蓄積:「休みたいのに休めない」「もっとプライベートな時間が欲しい」という欲求不満が募り、慢性的なストレス状態に陥りやすくなります。
特に、現代社会では、仕事のプレッシャーや責任も増大する傾向にありますから、それに見合った休息がなければ、心身のバランスを保つことは非常に難しいですよね。
仕事のために生きているわけではない、という価値観を大切にしたい方にとって、ワークライフバランスの崩壊は、大きな精神的な負担となり得ます。一時的なものであれば耐えられても、何年もの間、この状態が続くとなると、最終的には心身の健康を損ない、仕事そのものが嫌になってしまう可能性も否定できません。
「自分は体力があるから大丈夫」と思う方もいるかもしれませんが、それはあくまで一時的なものかもしれません。長期的な視点で、ご自身の心身の健康と生活の質を守るためにも、ワークライフバランスを重視するなら、年間休日105日という環境は慎重に検討すべきだと言えるでしょう。

【理由④】有給休暇が取りにくい雰囲気がある可能性
法律で定められた権利である「有給休暇」。従業員であれば、誰もが取得できる大切な休暇制度ですよね。しかし、年間休日105日という会社では、この有給休暇が「取りにくい雰囲気」がある可能性が高いんです。
もともと年間休日が少ないということは、それだけ会社全体として「人が休みを取る」ことに慣れていない、あるいは「休むと業務が回らない」という前提があるのかもしれません。
具体的には、次のような状況が考えられます。
- 人手不足:慢性的な人手不足の会社では、「あなたが休むと、他の人の負担が増える」という暗黙のプレッシャーを感じやすいでしょう。
- 業務が属人化:特定の業務を一人しか担当できない状態だと、その人が休むことで業務が滞り、有給申請が通りにくくなることがあります。
- 上司や同僚が有給を取らない:上司や先輩がほとんど有給を取らない雰囲気だと、自分も取りづらく感じてしまいますよね。
- 業務が忙しすぎる:常に業務に追われている状況では、「今、休んでいる場合じゃない」という気持ちになり、有給申請を躊躇してしまうことがあります。
「年間休日105日の職場で、有給消化率が低いのは当たり前でした。上司も先輩もほとんど取らないし、申請しても『今忙しいから無理だ』と言われることが多くて…。結局、ほとんど消化できませんでした。」
このような状況では、たとえ有給休暇が法定通りに付与されていても、実際に取得することが難しくなってしまいます。有給休暇は、心身のリフレッシュや、緊急時のために非常に重要なものです。それが十分に活用できないとなると、ますます休息不足に陥りやすくなりますし、万が一のときに困ってしまう可能性もあります。
入社前には、「有給休暇の取得状況はどうですか?」と質問するだけでなく、可能であれば、面接時に社員の雰囲気や、オフィス内の様子から、実際に休みが取りやすいかどうかをそれとなく確認してみることも大切ですよ。
【理由⑤】長期的なキャリア形成に悪影響が出かねない
仕事は、単にお金を稼ぐためだけのものではありません。自己成長を促し、スキルを磨き、将来のキャリアを形成していくための大切なステップですよね。しかし、年間休日105日の環境では、長期的なキャリア形成に悪影響が出かねないという側面があるんです。
なぜ年間休日105日がキャリア形成に影響を与えるのでしょうか?
- 自己投資の時間の不足:
スキルアップのための学習や資格取得、外部セミナーへの参加など、自己投資には時間が必要です。しかし、休みが少なく、日々の業務で疲弊していると、そのための時間を確保するのが難しくなります。 - 視野が狭まる可能性:
プライベートな時間が少ないと、新しい情報に触れたり、異業種の人と交流したりする機会が減ってしまいます。結果として、自分の業界や会社のことしか見えなくなり、視野が狭まってしまう可能性があります。 - 疲労による成長の停滞:
常に疲れている状態では、新しい知識を吸収したり、複雑な課題に取り組んだりする意欲が低下し、本来持っている成長スピードが鈍化してしまうかもしれません。 - 転職活動への影響:
もし将来的に転職を考えることになった場合、休みが少ないと転職活動のための時間(情報収集、面接など)を確保するのが難しくなります。また、疲れ切った状態では、面接でのパフォーマンスにも影響が出かねません。
「仕事は大変だけど、スキルアップのために勉強したいと思っていました。でも、毎日疲れて帰ると何もする気にならず、結局惰性で働くだけに。このままでは将来が不安になってきました。」
このような声からもわかるように、日々の業務に忙殺され、自己成長のための時間が取れないことは、長期的に見てあなたの市場価値を停滞させてしまうリスクがあります。特に若い時期は、将来の選択肢を広げるためにも、自己投資の時間を確保することが非常に重要です。年間休日105日の環境が、あなたのキャリアプランと合致しているか、よく考えてみてくださいね。
【理由⑥】友人や知人との比較で劣等感を感じることも
私たちの精神的な健康には、社会的なつながりや、周囲との比較も少なからず影響を与えますよね。年間休日105日の会社で働いていると、友人や知人との比較で、劣等感を感じてしまうこともあるかもしれません。
多くの会社では、土日・祝日が休みとなる「完全週休2日制」が定着しています。そのため、あなたの友人や学生時代の仲間は、カレンダー通りの大型連休を楽しんだり、週末に趣味の活動に興じたり、家族と過ごしたりしているかもしれません。
そんな時、あなたは…
- ゴールデンウィークやお盆に友人が旅行の計画を立てているのに、自分は出勤している
- 週末のイベントに誘われても、土曜出勤のために参加できないことがある
- 友人が長期休暇を取って海外旅行に行っている話を聞いて、羨ましく思う
- SNSで友人が楽しそうに休日を過ごしている投稿を見て、複雑な気持ちになる
といった経験をするかもしれません。
これは、あなたが頑張っていないわけでも、能力が低いわけでもありません。ただ、会社の休日制度の違いによるものですが、それが心理的な負担となる可能性は十分にあります。
「GWやお盆の時期は本当に辛かったです。みんなが楽しそうにしているのを見ると、自分は何のためにこんなに頑張っているんだろうって虚しくなりました。だんだん、休みが合う友達としか遊ばなくなって、人間関係も少し変わってしまいましたね。」
このような心理的なストレスは、日々の生活の満足度を低下させ、仕事へのモチベーションにも影響を与えかねません。もちろん、他者との比較は健康的なことではありませんが、社会生活を送る上で避けて通れない部分もありますよね。
もしあなたが、友人との付き合いや、一般的なライフスタイルとの比較を強く意識するタイプなのであれば、年間休日105日という環境は、精神的な負担となる可能性が高いことを理解しておく必要があるでしょう。
【理由⑦】離職率が高く、人材が定着しにくい傾向がある
年間休日が少ない職場は、一般的に「離職率が高い」「人材が定着しにくい」という傾向が見られます。これは、休日が少ないことによる様々なデメリット(休息不足、プライベートの時間の減少、ワークライフバランスの崩壊など)が積み重なり、従業員が働き続けることに限界を感じてしまうためです。
人が頻繁に入れ替わる職場環境は、あなたが働く上で以下のような悪影響を及ぼす可能性があります。
離職率が高い職場でのデメリットは、
- 業務負担の増加:
人が辞めるたびに、残されたメンバーの業務負担が増加します。新しい人が入ってきても、すぐに戦力になるわけではないため、一時的に忙しくなる期間が続くことになります。 - 人間関係の構築の難しさ:
せっかく良い人間関係を築いても、すぐに相手が辞めてしまうと、寂しさを感じたり、新しい人との関係をまた一から築き直す必要があったりします。 - スキルやノウハウの蓄積が困難:
経験者が辞めてしまうと、その人が持っていた知識やノウハウが失われ、組織としての成長が停滞する可能性があります。新しい人が入ってきても、教育に時間がかかり、効率が落ちることも。 - モチベーションの低下:
周囲の人が次々と辞めていく姿を見ると、「自分もいつか辞めるのかな」「この会社に未来はあるのかな」と不安になり、自身のモチベーションも低下してしまう可能性があります。 - 残業が増えやすい:
人手不足が常態化するため、恒常的に残業が多くなり、さらに休日が減るという悪循環に陥ることもあります。
「入社して半年で同期が何人も辞めていきました。そのたびに業務が自分にのしかかってきて、どんどん忙しくなって…。結局、私もこの会社に長くいるのは無理だと感じてしまいました。」
このように、離職率が高い環境は、あなた自身の働き方や精神状態にも大きな影響を与えかねません。長く安心して働きたい、腰を据えてキャリアを築きたいと考えているのであれば、年間休日が少ない会社を選ぶ際には、この「人の定着率」にも十分注意を払う必要があるでしょう。

それでも年間休日105日の道を選ぶなら?後悔しないための賢い働き方
ここまで、年間休日105日に潜むデメリットや「やめとけ」と言われる理由をたくさんお話ししてきました。しかし、もちろん、仕事内容や給与、人間関係など、休日日数だけでは測れない魅力を持つ会社も存在します。
もし、それでも「私は年間休日105日の会社で働きたい!」、あるいは「この会社でしかできない仕事がある」と考えているなら、後悔しないためにぜひ知っておいてほしい賢い働き方や、確認すべきポイントがあります。ここからは、その重要なアドバイスをお伝えしていきますね。
入社前に有給休暇の取得状況を徹底確認する
年間休日が少ない会社で働く上で、非常に大切なのが「有給休暇の取得状況」を徹底的に確認することです。年間休日が少なくても、有給休暇がきちんと取得できれば、ある程度のプライベートな時間は確保できるはずですよね。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 有給休暇の平均取得日数:
過去1年間の社員全体の平均取得日数を質問してみましょう。数値で明確に示してもらえるのが理想です。 - 有給休暇の取得しやすい雰囲気があるか:
「取得できます」という回答だけでなく、「実際に皆さんはどのように使っていますか?」「長期休暇は取れますか?」など、具体的に質問して、取得しやすい雰囲気があるのかを探りましょう。
面接の場で、現場の社員の方に直接質問できる機会があれば、よりリアルな声が聞けるかもしれません。 - 有給休暇の申請方法と承認プロセス:
「申請したらすぐに通るのか」「何か月も前から申請する必要があるのか」「上司の承認が必須で、なかなか通らないことはないか」など、具体的なフローを確認しておくと安心です。 - 有給消化率が高い部署や社員がいるか:
もし、特定の部署や社員だけが有給を多く取得できているのであれば、それは部署や上司によって取得しやすさが大きく異なる可能性を示唆しています。
法律で有給休暇の取得が義務付けられていますが、実態としてそれが機能しているかどうかは、会社によって大きく異なります。形式的な制度だけでなく、実際に「取得できる文化」があるかどうかをしっかりと見極めることが、後悔しないための重要なポイントですよ。
残業時間の実態を詳しく調べる
年間休日が少ない会社では、日々の労働時間、特に「残業時間」がどのくらい発生しているのか、その実態を詳しく調べておくことが極めて重要です。休日の少なさに加えて、残業が多いとなると、心身の負担は計り知れません。
確認すべき点は多岐にわたりますが、特に注意してほしいのは、
- 月平均の残業時間:
会社が提示する月平均の残業時間だけでなく、可能であれば、部署や職種ごとの実態についても質問してみましょう。 - 繁忙期と閑散期の残業時間:
一年を通して残業時間が一定ではない場合があります。繁忙期にはどのくらいの残業が発生するのか、その期間はどれくらい続くのかを確認しましょう。 - 残業代の支払いについて:
残業代はきちんと支払われるのか、固定残業代(みなし残業代)が含まれている場合は、何時間分で、それを超えた場合の支払いはどうなるのか、明確に確認することが大切です。 - サービス残業の有無:
口コミサイトや転職エージェントを通じて、サービス残業の有無や、残業申請しにくい雰囲気がないかなどを、可能な範囲で情報収集しましょう。 - 深夜・休日出勤の頻度:
特別な事情での深夜勤務や休日出勤があるのか、その際の賃金や代休の取得はどうなっているのかも確認しておくと安心です。
「残業はほとんどありません」と言われても、鵜呑みにせず、具体的な数字や実例を聞くようにしてください。もし残業が常態化している場合、年間休日105日という少ない休みが、さらに減るのと同じ状況になりかねません。あなたの心身を守るためにも、この残業の実態把握は、何よりも優先すべき事項ですよ。

仕事内容ややりがいで補えるか見極める
年間休日が少ないというデメリットを理解した上で、それでもその会社を選ぶのであれば、「仕事内容や、得られるやりがいが、休日の少なさを補って余りあるものなのか」を、ご自身の中で見極めることが非常に重要です。
どんなに休日が少なくても、
- どうしてもこの仕事がしたい!と心から思えるほど、仕事内容に魅力を感じている
- この会社でしか得られない経験やスキルがあると感じている
- 社会貢献性が高く、強い使命感を持って取り組める仕事である
- 関わる人々(顧客、同僚など)から大きな感謝や喜びを感じられる機会が多い
- 給与水準が非常に高く、経済的な目標達成に直結する
といった、明確な「やりがい」や「目的」があるのであれば、一時的に休日の少なさに耐えられるかもしれません。
ただし、以下の点に注意してください。
- 「やりがい」はいつまで続くか:
最初のうちはやりがいを感じられても、疲労やストレスが蓄積することで、その気持ちが薄れてしまう可能性もあります。長期的に見て、そのやりがいが持続可能なものなのかを冷静に考えてみましょう。 - 「成長」の定義:
「成長できる」という言葉だけで判断せず、具体的にどのようなスキルが身につき、それが将来のキャリアにどう役立つのかを明確にしてください。 - 給与と労働時間のバランス:
たとえ給与が高くても、それを時給換算してみたら、思ったほどではなかったというケースもあります。高い給与に見合うだけの労働を強いられる可能性も考慮しましょう。
「休みは少ないけど、本当にこの仕事が好きだから」という熱意は素晴らしいものですが、感情だけでなく、論理的な思考も加えることが大切です。ご自身のキャリアプランや、人生で何を最も大切にしたいのかを熟考し、休日の少なさを補って余りあるだけの「何か」が、その会社にあるのかどうかを慎重に見極めてくださいね。
自身の体力や精神力に自信があるか自己分析する
年間休日105日の環境は、間違いなく体力的・精神的に厳しいものとなりやすいです。そのため、その会社を選ぶのであれば、「ご自身の体力や精神力に自信があるか」を、客観的に自己分析することが非常に重要になります。
ご自身に問いかけてみてください。
- 過去に長時間の労働やストレスの多い環境で働いた経験はあるか?
その際、どのような心身の反応があったか、どのように乗り越えたかを振り返ってみましょう。 - ストレス耐性は高いか?
プレッシャーや多忙な状況でも、冷静に物事を対処できるタイプですか? ストレスを上手に発散できる方法を持っていますか? - 健康状態は良好か?
持病や慢性的な不調がないか、日頃から健康管理をしっかり行えているかを確認しましょう。 - 十分な睡眠時間を確保できるタイプか?
短時間睡眠でも大丈夫な人もいますが、多くの人にとって、睡眠不足はパフォーマンス低下や健康問題に直結します。 - 運動習慣やリフレッシュ方法を持っているか?
休日に気分転換できる趣味や、体を動かす習慣などがあれば、ストレスを軽減しやすいかもしれません。
「自分は若いから大丈夫」「根性があるから乗り切れる」と過信してしまうのは危険です。疲労やストレスは、目に見えない形で少しずつ蓄積し、ある日突然、心身の不調として現れることがあります。
「自分は体力には自信があったのですが、年間休日105日の会社で働き始めてから、毎週のように風邪をひいたり、朝起きるのが辛くなったりしました。無理がたたって、精神的にも不安定になってしまい、結局は退職せざるを得ませんでした。」
このような声からもわかるように、体力や精神力には個人差があり、また年齢とともに変化するものです。無理を重ねると、取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。ご自身の心と体の声に耳を傾け、本当に無理なく働き続けられる環境なのかを、冷静に判断してくださいね。
会社の文化や社員の雰囲気を事前に確認する
年間休日が少ない職場であっても、その会社の「文化や社員の雰囲気」が非常に良い場合、意外と働き続けられることもあります。逆に、休日が少なくて雰囲気が悪いとなると、それはまさに地獄ですよね。そのため、入社前にできる限り、その会社の文化や社員の雰囲気を確認しておくことが大切です。
確認方法としては、以下のようなものが考えられます。
- 面接時の雰囲気:
面接官や、もしあれば案内してくれた社員の方々の表情、言葉遣い、働き方に対する考え方などを注意深く観察しましょう。 - オフィス訪問や職場見学:
可能であれば、オフィスに訪問させてもらい、実際に社員が働いている様子や、休憩スペースの雰囲気などを自分の目で見てみましょう。社員同士の会話や、活気があるかどうかなどもヒントになります。 - 社員食堂や休憩所の利用:
もし利用できるのであれば、社員がどのように過ごしているか、会話が弾んでいるかなどを観察するのも良いでしょう。 - 企業口コミサイトやSNSでの情報収集:
匿名性が高い情報なので鵜呑みにはできませんが、複数の情報源から共通して見られる情報(例えば、「人間関係は良いが忙しい」「風通しは良い」など)は参考になる場合があります。 - OB/OG訪問やリファラル:
もし知人がその会社に勤めている、あるいは過去に勤めていたのであれば、リアルな話を聞くことができる最も有効な手段です。
人間関係が良好で、お互いを助け合う文化がある会社であれば、たとえ忙しくても、精神的な負担は軽減される可能性があります。また、仕事の成果を正当に評価してくれたり、感謝の言葉を伝えてくれたりする文化があれば、やりがいを感じながら働き続けられるかもしれません。
しかし、雰囲気は目に見えにくいものです。短い時間での判断は難しいかもしれませんが、五感をフル活用し、違和感がないか、自分に合うかどうかを慎重に判断してくださいね。
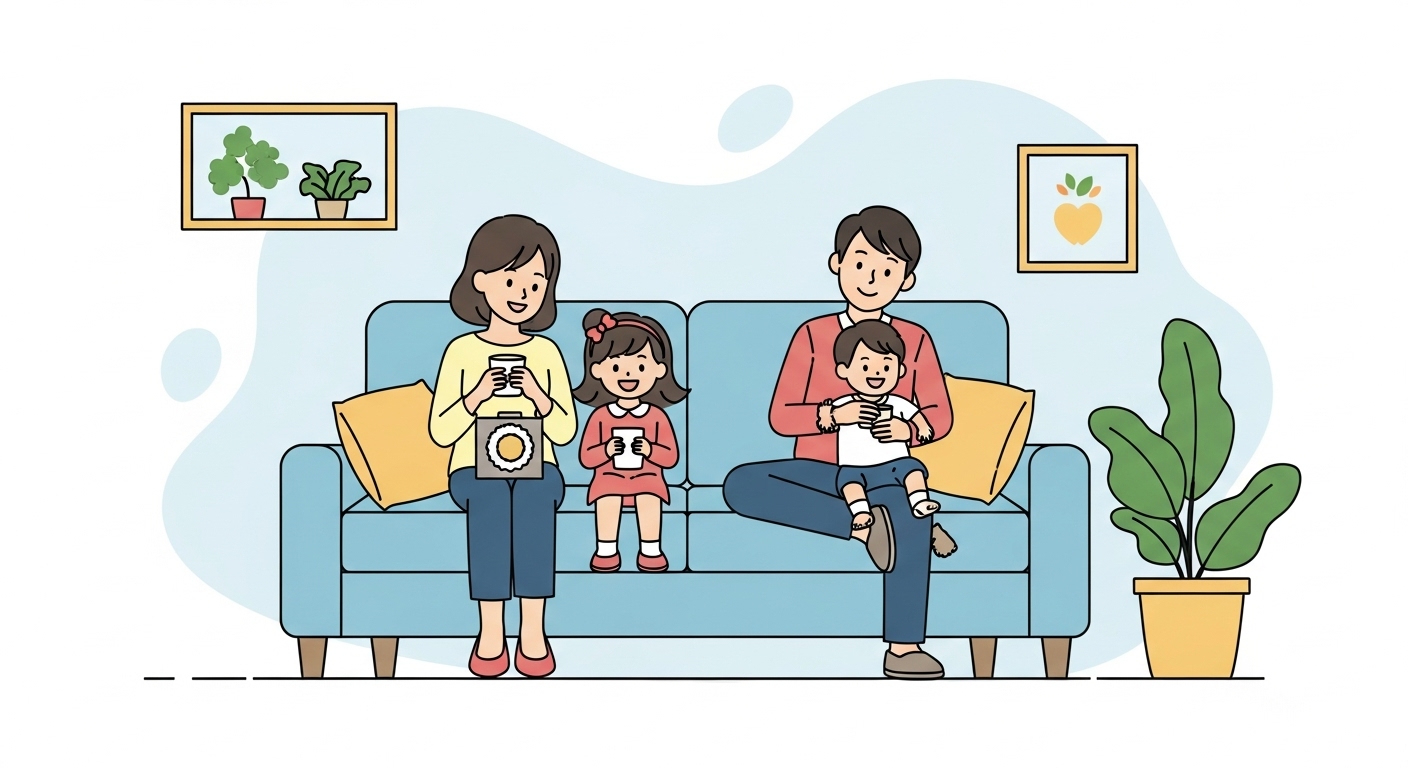
年間休日105日はやめとけ?その理由の総括
さて、ここまで年間休日105日について、その基本的な意味から、「やめとけ」と言われる具体的な理由、そしてもし年間休日105日の会社を選ぶ場合の賢い働き方まで、丁寧にお話ししてきました。
年間休日105日は、日本の労働基準法上は問題がないものの、一般的な企業と比較すると休日が少なく、多くのデメリットを伴う可能性があることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
年間休日105日の会社を検討する際に、特に心に留めておいてほしいポイントは、次の通りです。
- 年間休日105日は「完全週休2日制」とは異なり、祝日出勤や土曜出勤が含まれることが多いです。
- 労働基準法上の最低限の休日数は満たしていますが、心身の健康を維持するための十分な休息が取れない可能性が高いです。
- 趣味や家族との時間など、プライベートな時間が極端に少なくなり、生活の質が低下する恐れがあります。
- 仕事と私生活のバランスが崩れやすく、慢性的なストレスや疲労に繋がりやすい傾向があります。
- 法律で保障された有給休暇が、会社の実情として「取りにくい雰囲気」にある可能性が高いです。
- 自己投資やスキルアップの時間が確保できず、長期的なキャリア形成に悪影響が出るかもしれません。
- 友人や知人との休日の違いから、劣等感や孤独感を感じてしまう可能性もあります。
- 離職率が高く、人材が定着しない職場環境は、残された従業員の負担増大やモチベーション低下に繋がりかねません。
「やめとけ」という言葉は、安易な選択に対する警鐘でもあります。年間休日105日の会社が全て悪いというわけではなく、その特性を理解せずに飛び込んでしまうことが、失敗や後悔につながるということなんです。
ご自身の働き方に対する価値観、仕事で得たいもの、そして何よりもご自身の心身の健康を第一に考えて、慎重に判断することが、後悔しないための最も大切なステップだと言えるでしょう。
この記事が、皆さんがご自身のキャリアを考える上で、少しでもお役に立てたなら、私としてもうれしいです。