こんにちは。大学生活を送る中で、「今の大学、なんだか違うかも…」「もっと専門的に学びたい分野が見つかった」と感じ、現状を変えたいと思うことはありませんか?
そんな時、選択肢の一つとして「大学編入」が頭に浮かぶかもしれません。今の大学よりもレベルの高い大学へ移ったり、学びたい分野を求めて環境を変えたりと、未来への可能性を広げる魅力的な道に思えますよね。
しかし、インターネットで「大学編入」と検索すると、「やめとけ」「後悔」「孤独」といった、少し不安になる言葉が並びます。これは一体なぜなのでしょうか。この記事では、大学編入という制度の光と影、特に「やめとけ」と言われる厳しい現実について、一つひとつ丁寧に解き明かしていきたいと思います。
この記事でお伝えしたいこと
- 大学編入とは?その仕組みと知られざる実態
- なぜ大学編入は「やめとけ」と言われるのか?7つの具体的な理由
- それでも編入を目指す人が後悔しないための心構え
- 大学編入という選択肢を考える上での総括
大学編入とは?その仕組みと知られざる実態
まず、「大学編入」がどのような制度なのか、基本的なところからご説明しますね。「名前は聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない」という方も、きっと多いのではないでしょうか。
大学編入の基本的な仕組み
大学編入とは、在籍している大学や短大、専門学校などから、別の大学の2年次や3年次に移籍して入学する制度のことです。一般的には、4年制大学の2年次を修了した学生が、他の大学の3年次に編入する「3年次編入」が主流となっています。
一般入試が主に高校生を対象とした学力試験であるのに対し、編入試験は大学生や社会人などを対象としており、その内容は大きく異なります。
- 試験科目:専門科目、小論文、面接、語学(特に英語)が中心。大学・学部によって内容は千差万別です。
- 試験時期:一般的に6月~11月頃に行われることが多く、大学によってバラバラです。
- 募集人数:各学部で若干名しか募集しないことが多く、非常に狭き門となります。
このように、一般入試とは全く違う、特殊で情報戦の側面が強い入試形態だということを、まず知っておくことが大切です。

なぜ大学編入は魅力的に見えるのか
では、なぜ多くの人がこの厳しい道に魅力を感じるのでしょうか。その動機は人それぞれですが、主に以下のようなものが挙げられます。
- 学歴のステップアップ:いわゆる「学歴ロンダリング」とも言われますが、より偏差値の高い大学に移ることで、最終学歴を更新したいという動機です。
- 専門分野の変更・深化:大学で学ぶうちに、本当に学びたい専門分野が見つかり、その分野に強い大学へ移りたいと考えるケースです。
- 環境のリセット:今の大学の人間関係や環境に馴染めず、心機一転、新しい場所で再スタートを切りたいという思いから。
- 経済的な理由:短大や専門学校を卒業後、4年制大学で学びを続けたい場合など。
どの動機も、現状をより良くしたいという前向きな気持ちから生まれるものですよね。しかし、その思いの先に、想像以上に厳しい現実が待ち受けていることを、これから詳しくお話ししていきます。
大学編入はやめた方がいい!勧められない7つの理由
それでは、ここからが本題です。なぜ、人生を変えるチャンスにもなり得る大学編入が、「やめとけ」とまで言われてしまうのでしょうか。その理由を7つに分けて、詳しく見ていきましょう。
【理由①】情報が少なく孤独な戦いになりやすい
大学編入を目指す上で、まず最初にぶつかる大きな壁が「情報不足」です。高校生が大学受験をする際は、予備校や高校が手厚くサポートしてくれますし、周りにも同じ目標を持つ仲間がたくさんいますよね。
しかし、編入は全く違います。編入専門の予備校は少なく、大学のキャリアセンターも十分なノウハウを持っていないことがほとんどです。そのため、基本的には全ての情報を自分で集めなければなりません。
- 過去問が公表されておらず、入手が困難
- 面接で何を聞かれるのか、情報がない
- 同じ目標を持つ仲間が見つからず、モチベーション維持が難しい
大学の友人たちがサークルやアルバイトを楽しんでいる中、たった一人で図書館にこもり、先の見えない試験勉強を続ける…。この精神的な孤独感は、想像以上に辛いものです。この孤独に耐えられず、途中で諦めてしまう人も少なくないんですよ。

【理由②】編入後の「単位認定」が地獄の始まりになることも
無事に編入試験に合格したとしても、安心するのはまだ早いです。次に待ち受けているのが、「単位認定」という大きな関門です。
これは、前の大学で取得した単位が、編入先の大学でどれだけ卒業単位として認められるか、という手続きです。ここで大きな問題が起こります。
「前の大学で62単位取ったから、残りの単位を取れば卒業できる」という単純な話ではないんです。編入先の大学のカリキュラムによっては、取得した単位の多くが認められず、3年次に編入したにも関わらず、1・2年生向けの必修科目を大量に履修し直さなければならないケースが頻繁に起こります。
その結果、どうなるかと言うと…
「3年生なのに、授業は1年生や2年生と一緒。周りは年下ばかりで気まずいし、専門科目と基礎科目を同時に履修するので、時間割はパンパン。ゼミや研究室の活動と両立できず、結局4年間での卒業を諦めました…。」(編入経験者 Aさん)
編入によって、むしろ卒業までの道のりが険しくなり、最悪の場合、留年してしまうリスクがあることは、必ず知っておかなければいけない事実です。
【理由③】完成された人間関係の中に飛び込む疎外感
3年次編入の場合、あなたはすでに2年間を共に過ごし、固い絆で結ばれたコミュニティの中に、たった一人で入っていくことになります。これは、想像以上に精神的なエネルギーを消耗します。
周りの学生は、すでにお昼を一緒に食べる仲間や、一緒に授業を受けるグループが出来上がっています。サークルも、3年生から新しく入るのは気まずさを感じてしまうかもしれません。話しかけようにも、「あの人誰?」「編入生らしいよ」と、どこか壁を感じてしまうことも。

もちろん、親切に接してくれる人もいますが、「編入生」という特別な目で見られることから完全に逃れるのは難しいでしょう。授業の情報交換や、過去問の入手など、友人関係が重要な場面で不利になることもあります。この常に感じる疎外感やアウェー感に耐え切れず、大学に行くのが億劫になってしまう人もいるんです。
【理由④】学力差と授業のレベルに打ちのめされる
特に、今の大学よりもレベルの高い大学へ編入した場合、この問題に直面する可能性が高いです。編入試験は科目数が少ないため、その科目だけを徹底的に対策して合格することも可能です。
しかし、編入先の学生たちは、厳しい一般入試を勝ち抜いてきた人たちです。彼らは、あなたが学んでこなかった幅広い基礎知識を、1・2年生の間にしっかりと身につけています。
授業では、当然のように専門用語が飛び交い、ディスカッションでは周りの学生が鋭い意見を次々と述べる…。その中で、自分だけが話についていけず、基礎学力の圧倒的な差を痛感し、自信を喪失してしまうことがあります。
「試験には合格できたけど、本当の実力は周りに及ばない」という劣等感に、長く苦しむことになるかもしれません。
【理由⑤】編入後すぐに始まる就職活動での不利
3年次編入の場合、大学生活に慣れる間もなく、すぐに就職活動の準備が始まります。これが、編入生にとって非常に不利に働くことがあるんです。
- 情報戦での遅れ:就活は情報戦です。しかし、頼れる友人が少ない編入生は、インターンシップの情報や、OB・OG訪問のノウハウなどを得にくくなります。
- 自己分析の時間不足:新しい環境への適応と、大量の単位取得に追われ、自分の将来についてじっくり考える時間が十分に取れません。
- 面接での「なぜ?」という質問:面接では、ほぼ100%「なぜ大学を編入したのですか?」と聞かれます。ここで、面接官を納得させられる、前向きで論理的な説明ができなければ、「計画性がない」「忍耐力がない」とマイナスの評価を受けてしまう可能性があります。
周りの学生が2年間かけて築いてきたキャリアプランや人脈がないまま、いきなり就活の最前線に立たされる。これは、あまりにもハンデが大きい戦いだと言わざるを得ません。

【理由⑥】大学生活の「美味しいところ」を経験できない
大学生活の楽しさは、勉強だけではありませんよね。1年生の時の初々しい出会いや、2年生になって少し慣れてきた頃のサークル活動、学園祭の準備など、振り返ればキラキラした思い出がたくさんあります。
しかし、編入生はこれらの「青春」とも言える期間を経験することができません。編入後は、単位取得と就職活動に追われる、大学生活で最も忙しく、精神的にも大変な時期からのスタートとなります。
周りの友人たちが楽しそうに大学生活の思い出を語る中、自分には共有できる思い出がない…。そんな寂しさを感じることもあるかもしれません。「もっと普通の大学生活を送りたかった」と後悔する可能性も考えておく必要があります。
【理由⑦】「逃げの編入」は何も解決しない
最後に、これが最も本質的な理由かもしれません。「今の大学の人間関係が嫌だ」「授業がつまらない」といった、現状からの「逃げ」の気持ちだけで編入を目指すのは、とても危険です。
なぜなら、環境を変えても、あなた自身が変わらなければ、結局同じ問題にまた直面する可能性が高いからです。新しい大学でも、気の合わない人はいるでしょうし、つまらないと感じる授業もあるかもしれません。
問題の根本的な原因は、環境ではなく、自分自身のコミュニケーションの取り方や、物事への向き合い方にあるのではないか?この問いから目をそらして、安易に環境のせいにしてしまうと、編入先でも同じ失敗を繰り返し、ただ時間とお金を無駄にしてしまうことになりかねません。
それでも大学編入を目指すあなたへ|後悔しないための心構え
ここまで、大学編入の厳しい現実をたくさんお話ししてきました。これらを読んで、「やっぱり自分には無理かもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。
ですが、もし、これらの困難を知った上で、それでも「挑戦したい」という強い意志があるのなら、その思いは本当に尊いものです。そんなあなたが後悔しないために、ぜひ心に留めておいてほしい心構えを3つお伝えします。
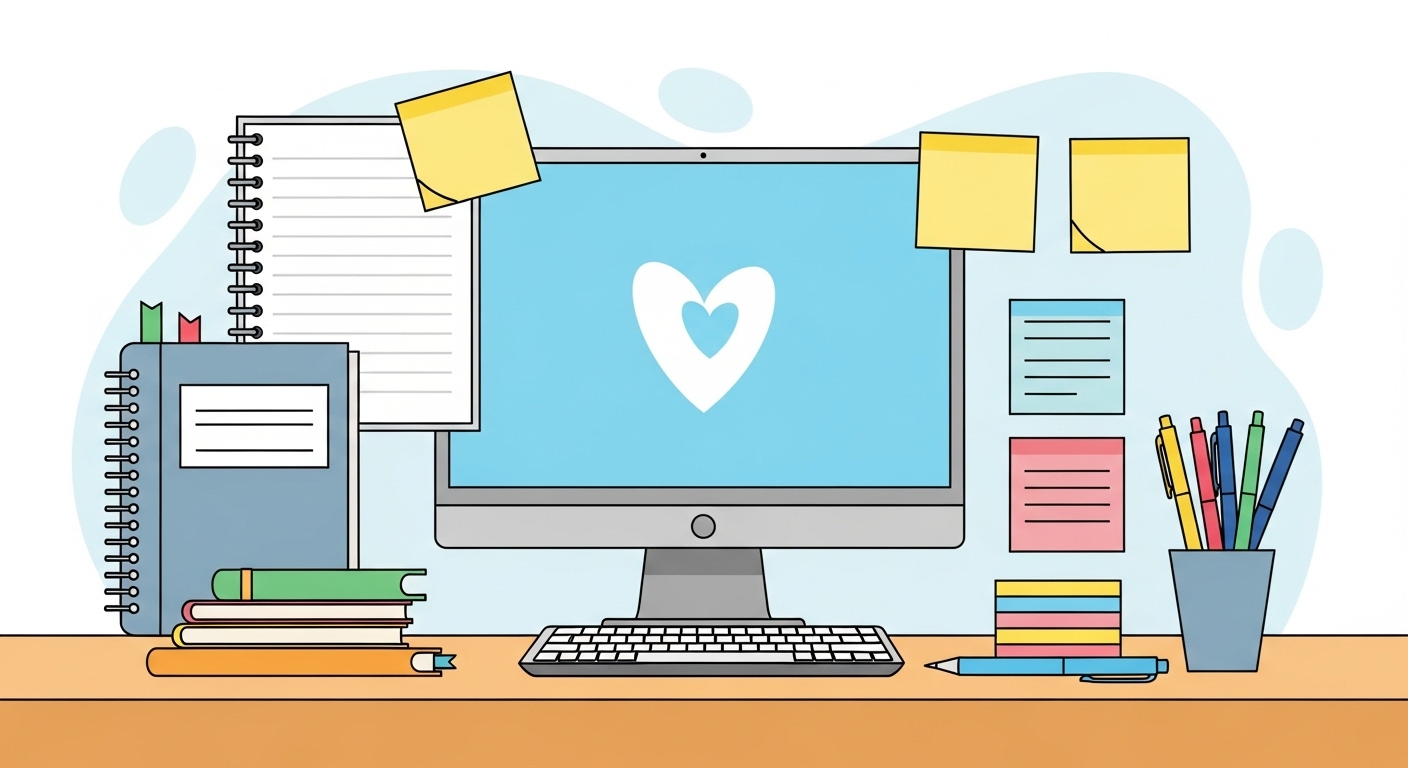
【心構え①】「なぜ編入するのか」という目的を徹底的に深掘りする
「今の大学が嫌だから」というネガティブな動機ではなく、「この大学の〇〇先生の下で、△△という分野を研究したい」という、具体的でポジティブな目的を持つことが何よりも重要です。
その目的が明確であればあるほど、辛い受験勉強を乗り越える力になりますし、編入後の面接や就職活動でも、あなたの熱意はきっと相手に伝わります。誰に聞かれても、自分の言葉で情熱的に語れる目的を見つけましょう。
【心構え②】編入後の生活を具体的に、厳しくシミュレーションする
合格後のバラ色のキャンパスライフを夢見るのではなく、むしろ、この記事で挙げたような厳しい現実を、自分の身に起こることとして具体的に想像してみてください。
もし単位認定が厳しかったら、どんな時間割になるだろう?友達が一人もできなかったら、どうやって情報を集める?就活で不利にならないために、今から何ができる?…このように、起こりうる最悪の事態を想定し、その対策を考えておくことで、実際に困難に直面した時も、冷静に対処できるはずです。
【心構え③】今の大学生活も全力で取り組む
「どうせ編入するから」と、今の大学の授業や人間関係をおろそかにするのは、絶対にいけません。今の大学で良い成績を収めることは、編入試験の出願条件を満たす上で必須ですし、面接での評価にも繋がります。
何より、今いる場所で頑張れない人が、新しい場所で頑張れるはずがないんです。今の環境でできる限りの努力をすることが、結果的にあなたの実力を高め、編入という次のステップへ繋がる一番の近道になるんですよ。
「大学編入はやめとけ」と言われる理由の総括
今回は、大学編入という選択肢について、その厳しい現実と「やめとけ」と言われる理由を詳しく解説させていただきました。
大学編入を安易に勧めることができない理由のまとめ
- 理由①:情報が極端に少なく、相談相手もいないため、孤独な戦いを強いられるから。
- 理由②:編入後の単位認定が厳しく、時間割が過密になったり、留年したりするリスクがあるから。
- 理由③:すでに完成している人間関係の中に入っていく必要があり、強い疎外感や孤独を感じやすいから。
- 理由④:周りの学生との基礎学力の差に愕然とし、授業についていけず自信を失うことがあるから。
- 理由⑤:編入後すぐに始まる就活で、情報不足や準備不足から不利になりやすいから。
- 理由⑥:大学生活の楽しい時期を経験できず、大変な時期からのスタートになるから。
- 理由⑦:現状からの「逃げ」が動機の場合、環境を変えても根本的な問題は解決しないから。
大学編入は、決して安易な「学歴リセットボタン」ではありません。むしろ、一般入試とは質の違う、険しく孤独な茨の道だと言えるかもしれません。
しかし、明確な目的と強い覚悟、そして周到な準備があれば、あなたの人生をより豊かな方向へ導いてくれる、価値ある挑戦にもなり得ます。この記事が、あなたが後悔のない選択をするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。



