こんにちは。皆さんは「外交官」と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか?世界中を飛び回り、各国の要人と渡り合う、華やかで知的なエリート…そんな姿を思い浮かべる方も多いかもしれませんね。
ですが、インターネットで「外交官」と検索すると、「やめとけ」「きつい」「後悔」といった、少し気になる言葉が一緒に表示されることがあります。これは一体どうしてなのでしょうか?
この記事では、多くの人が憧れる外交官という職業について、その華やかなイメージの裏に隠された厳しい現実や、「やめとけ」と言われる理由を、一つひとつ丁寧に解説していきたいと思います。憧れだけで目指す前に、ぜひ知っておいていただきたいお話です。
この記事でお伝えしたいこと
- 外交官とは?知られざる仕事のリアルな内容
- なぜ外交官は「やめとけ」と言われるのか?7つの具体的な理由
- それでも外交官を目指したい人が後悔しないための心構え
- 外交官という職業を選ぶ前に考えるべきことの総括
外交官とは?知られざる仕事内容と現実
まず、外交官がどのようなお仕事なのか、基本的なところからお話しさせてくださいね。外交官は、国家公務員の一種で、外務省に所属し、日本を代表して外国との交渉や交流を行う専門職です。
一般的に、外交官のキャリアは「本省勤務」と「在外公館勤務」の2つを交互に繰り返すことになります。
本省勤務(東京・霞が関)
日本の外交政策の企画・立案、外国から集められた情報の分析、関係省庁との調整、国会対応など、日本の外交の司令塔としての役割を担います。デスクワークが中心で、非常に地道な作業が多いんですよ。
在外公館勤務(海外の日本大使館や総領事館)
担当する国や地域の政府との交渉、情報収集、その国に進出している日本企業への支援、そして何より、海外に住む日本人の安全を守る「邦人保護」など、現場の最前線で活動します。広報文化活動として、日本の魅力を伝える役割もあるんです。
多くの方がイメージする「外交官」は、後者の在外公館でのパーティーや会合の姿かもしれません。ですが、その裏では膨大な量の報告書作成や事務作業に追われているのが実態なんです。

「国を代表する仕事」という響きはとても立派ですが、その実態は、華やかさよりも、むしろ地道さと責任の重さが際立つ職業だということを、まず知っておくことが大切だと思います。
外交官はやめた方がいい!勧められない7つの理由
それでは、ここからが本題です。なぜ、あれほど憧れの的である外交官が「やめとけ」と言われてしまうのでしょうか。その理由を7つに分けて、詳しく見ていきましょう。
【理由①】想像を絶する超難関試験と長い下積み期間
まず最初の壁は、そもそも外交官になること自体の難しさです。外交官になるには、外務省専門職員採用試験か、国家公務員採用総合職試験(院卒者・大卒程度)に合格する必要があります。
これらの試験は、数ある公務員試験の中でもトップクラスの難易度を誇ります。特に、求められる知識の範囲が非常に広いんです。
- 国際法、憲法、経済学などの専門知識
- 卓越した外国語能力(英語は必須、さらに専門言語の習得も求められます)
- 国内外の歴史や時事問題に関する深い教養
これらを何年もかけて勉強し、ようやく試験に臨むことになります。当然、倍率も非常に高く、合格できるのはほんの一握りの人だけです。
外務省の発表によると、例えば2023年度の外務省専門職員採用試験の申込者数は1,013名で、最終合格者は96名でした。単純計算でも倍率は10倍を超えており、いかに狭き門であるかがわかりますね。(出典:外務省 令和5年度外務省専門職員採用試験の実施結果)
そして、晴れて合格してもすぐに第一線で活躍できるわけではありません。そこから長い研修期間が始まります。国内での研修後、海外の大学などで2~3年間、担当言語や地域の研究に専念する「在外研修」に出るのが一般的です。
一人前の外交官として本格的に仕事ができるようになるまでには、採用から何年もかかる…。この長い道のりを乗り越える覚悟がなければ、途中で挫折してしまう可能性が高いんです。
【理由②】24時間365日続く「国」を背負う重圧と過酷な労働
外交官の仕事は、決して9時から5時で終わるものではありません。特に在外公館に勤務していると、その責任の重さから、常に緊張状態を強いられることになります。
例えば、日本との間には大きな時差がありますから、本省との連絡のために深夜や早朝に働くことは日常茶飯事です。また、担当国でテロや災害、大きな事件・事故が発生すれば、昼夜を問わず即座に対応しなければなりません。邦人の安否確認や支援のために、危険な現場へ向かうことだってあります。

ある元外交官の方は、このように語っています。
「携帯電話は24時間肌身離さず持っていました。いつ緊急の呼び出しがあるかわからないからです。休暇中でも、担当地域の情勢が緊迫すれば、すぐに職場に駆けつけなければいけない。心から休まる時間はほとんどありませんでした。」
常に「日本を代表している」という意識を持ち、一つのミスが国益を損なうかもしれないというプレッシャーの中で働き続けることは、私たちが想像する以上に心身を消耗させます。この精神的なタフさがなければ、務まらない仕事なんです。
【理由③】家族のキャリアと人生を巻き込む頻繁な転勤
外交官にとって、転勤は宿命です。およそ2~3年ごとに、本省勤務と在外公館勤務を繰り返します。つまり、2~3年ごとに海外へ引っ越し、また日本へ戻ってくるという生活が、定年まで続くことになるんです。
これは、独身の間はまだ良いかもしれませんが、家庭を持つと非常に大きな問題になります。
- 配偶者のキャリア: 転勤のたびに仕事を辞めなければならず、キャリアを継続することが極めて困難になります。配偶者の自己実現を犠牲にしてしまうケースは少なくありません。
- 子どもの教育: 現地の学校、日本人学校、インターナショナルスクールなど、選択肢はありますが、数年での転校は避けられません。言語の壁やいじめ、アイデンティティの形成に悩む子どももいます。
- 友人関係のリセット: 親も子も、せっかく築いた人間関係が数年でリセットされてしまいます。新しい環境に毎回適応していくのは、大きなストレスになります。

家族の誰かが「もう海外での生活は嫌だ」と感じても、仕事を辞めない限り転勤は続きます。この問題から、家族が一緒に暮らすことを諦めて単身赴任を選ぶ外交官も多いのですが、それもまた寂しい選択ですよね。
自分一人の覚悟だけではどうにもならない、家族全員の人生を巻き込む。これが、外交官という職業の最も厳しい側面の一つだと言えるでしょう。
【理由④】身の危険と隣り合わせの赴任地
「海外勤務」と聞くと、パリやニューヨーク、ロンドンといった先進国の華やかな都市を思い浮かべるかもしれません。もちろん、そういった国に赴任する機会もあります。
しかし、外交官は日本の国益のために世界中に派遣されます。それは、政情が不安定な国、紛争やテロの危険がある国、衛生環境や医療水準が低い国も含まれるということです。
外務省は世界各国の危険情報として「海外安全ホームページ」を公開しています。レベル3の「渡航中止勧告」やレベル4の「退避勧告」が出ているような、非常に危険な地域にも日本の大使館は存在し、そこで働く外交官がいるのです。
実際に、過去には海外で外交官がテロの犠牲になったり、襲撃事件に巻き込まれたりする悲しい出来事も起きています。自分の希望が必ず通るわけではなく、時には命の危険を感じるような場所で、国のために働かなければならない可能性もゼロではないんです。
「どんな国へ行くことになっても、職務を全うする」という強い使命感がなければ、恐怖心に押しつぶされてしまうかもしれません。
【理由⑤】華やかさとは程遠い地味な業務の連続
外交官の仕事として、各国の要人との会食やレセプション(歓迎会)への出席も確かにあります。しかし、それは仕事全体のほんの一部に過ぎません。
実際の業務の多くは、非常に地道なものです。
- 膨大な量の情報収集と、それをまとめるための報告書作成
- 本省や他機関との連絡・調整業務
- 会議のための資料準備や議事録作成
- ビザ(査証)の発給業務
- 経費の精算など、細々とした会計事務

特に若手の頃は、こうした事務作業が仕事の大半を占めることも少なくありません。「世界を股にかけて活躍したい」という大きな志を持って入省したのに、毎日パソコンと書類に向き合うばかりで、「国と国を繋ぐ」というより「書類と書類を繋ぐ」仕事だと感じてしまう…そんなギャップに苦しむ人もいるようです。
きらびやかなイメージだけでこの世界に飛び込むと、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。
【理由⑥】厳しく制限されるプライベートと人間関係
外交官は、国家公務員として常に品位を保つことが求められます。これは、勤務時間中だけでなく、プライベートの時間においても同じです。
不用意な言動が、日本という国全体の評判を落としかねないからです。そのため、SNSでの発信や、私的な交友関係にも細心の注意を払わなければなりません。何気ない一言が、外交問題に発展する可能性だってあるのです。
赴任先での生活も、自由気ままというわけにはいきません。特に小さな国や日本人コミュニティが限られている場所では、どこで誰に見られているかわからないという窮屈さを感じることもあるそうです。公使の別なく、常に「日本の顔」として振る舞うことが求められるんですね。
また、在外公館という閉鎖的な環境での人間関係に悩む人もいます。どこへ行っても同じメンバーと顔を合わせることになるため、一度関係がこじれると修復が難しく、大きなストレスの原因になることもあるようです。
【理由⑦】高すぎる理想と「こんなはずじゃなかった」という現実
外交官を目指す方は、「国際平和に貢献したい」「日本のプレゼンスを高めたい」といった、非常に高い理想や志を持っていることが多いと思います。それは本当に素晴らしいことです。
しかし、現実は巨大な行政組織の一員として働くことになります。自分が正しいと思ったことが、必ずしも組織の方針と一致するとは限りません。硬直的な組織文化や、複雑な省庁間の力学の中で、自分の無力さを感じてしまう場面も少なくないでしょう。
「もっとダイナミックに世界を動かす仕事だと思っていました。でも実際は、数多くの承認プロセスを経て、ようやく一つの文書が出来上がるような世界。自分の意見が政策に反映されることなんて、ほとんどありませんでした。次第に、自分は何のためにここにいるんだろう、と考えるようになりました。」(元外務省職員)
壮大な理想と、組織の歯車として働く地道な現実。この大きなギャップを受け入れられず、志半ばで去っていく人がいるのも事実です。理想の高さゆえに、現実との落差に深く傷ついてしまうのかもしれませんね。
それでも外交官を目指すあなたへ|後悔しないための心構え
ここまで、外交官という職業の厳しい側面をたくさんお話ししてきました。これらを読んで、「やっぱり自分には無理かもしれない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
でも、もし、これらの困難を知った上で、それでも「挑戦したい」という気持ちが揺るがないのであれば、その思いはとても尊いものだと思います。そんなあなたに、後悔しないために考えてみてほしいことがあります。
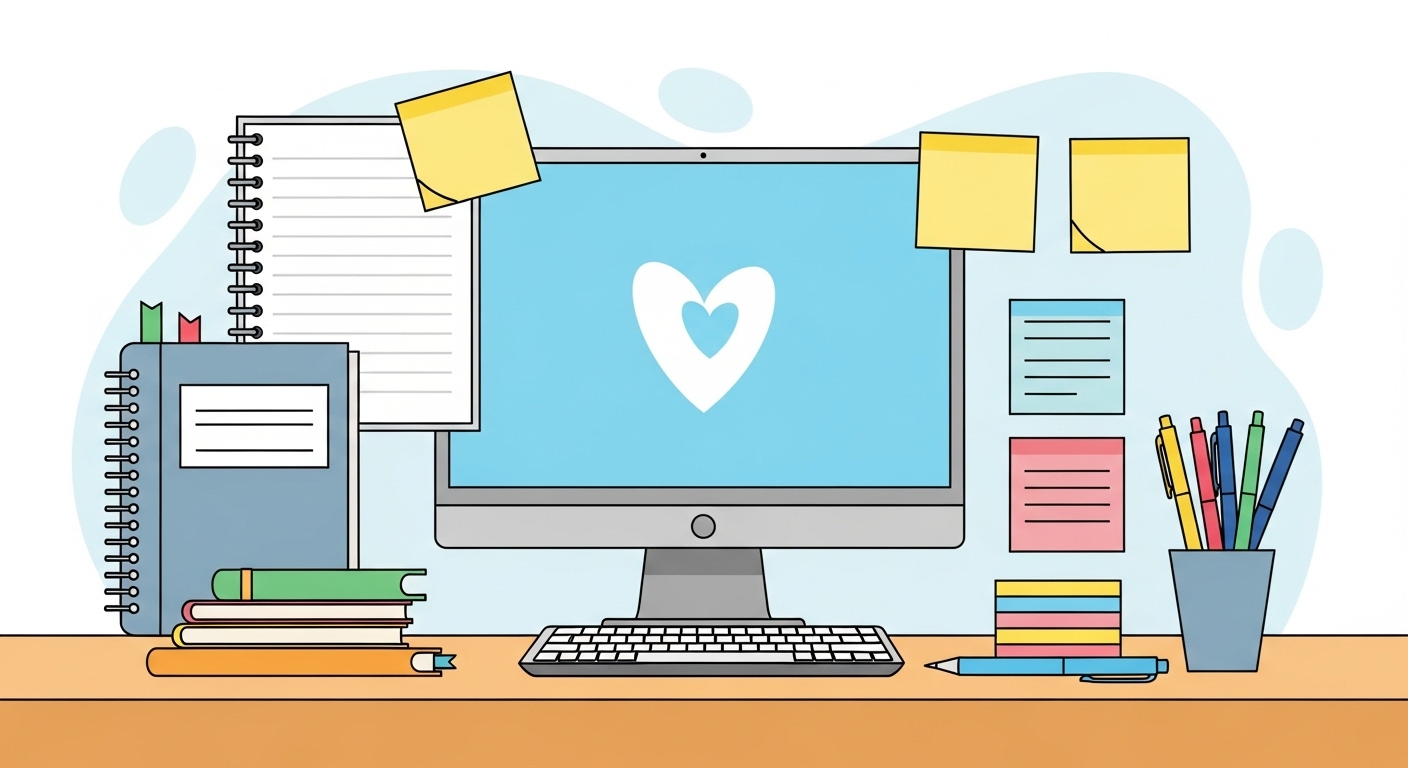
【心構え①】「なぜ外交官なのか」を深く突き詰める
「かっこいいから」「海外で暮らしたいから」といった漠然とした憧れだけでは、先ほどお話ししたような困難を乗り越えるのは難しいでしょう。なぜ、他の仕事ではなく、外交官でなければならないのか。自分なりの答えを、自分の言葉で説明できるようにしておくことが大切です。
外交官として何を成し遂げたいのか、その核となる動機が明確であれば、困難に直面したときの大きな支えになってくれるはずです。
【心構え②】ネガティブな情報から目をそらさない
憧れの職業については、つい良い面ばかりを見てしまいがちです。ですが、本当に目指すのであれば、むしろネガティブな情報や厳しい現実にこそ、真剣に向き合うべきです。
この記事で挙げたような大変さや、元外交官の方々の苦労話などを積極的に集めてみてください。その上で、「自分なら耐えられるか」「どうすれば乗り越えられるか」をシミュレーションしてみることが、後悔しないための第一歩になります。
【心構え③】家族と未来について真剣に話し合う
もしあなたにパートナーや家族がいるのなら、外交官を目指すことについて、正直に、そして真剣に話し合う時間を持つことが不可欠です。先ほどお話しした通り、外交官の仕事は家族の人生を大きく左右します。
頻繁な転勤、配偶者のキャリア、子どもの教育…。これらの問題について、家族がどう感じているのか、どんな協力が得られそうか、あるいはどんなことが不安なのかを、しっかりと共有してください。家族の理解と応援がなければ、この道を進むことは非常に困難です。
「外交官はやめとけ」と言われる理由の総括
今回は、華やかなイメージとは裏腹の、外交官という仕事の厳しい現実についてお話しさせていただきました。
外交官を勧められない理由まとめ
- 理由①:合格までが非常に困難な上に、合格後も長い下積みが必要だから。
- 理由②:24時間体制の緊張と、国を背負う重圧が心身を消耗させるから。
- 理由③:頻繁な海外転勤が、配偶者のキャリアや子どもの教育など家族に大きな負担を強いるから。
- 理由④:紛争地域など、身の危険が伴う国へ赴任する可能性があるから。
- 理由⑤:仕事の多くは報告書作成などの地味な事務作業で、イメージとのギャップが大きいから。
- 理由⑦:高い理想と、組織の歯車として働く現実とのギャップに苦しみやすいから。
- 理由⑥:国家公務員としてプライベートが制限され、窮屈さを感じることがあるから。
外交官は、間違いなく国のために貢献できる、やりがいのある尊い仕事です。しかし、その裏には、並大抵ではない覚悟と努力、そして家族の犠牲が求められるという現実があります。
この記事が、安易な憧れだけで将来を決めてしまうことを防ぎ、ご自身の適性や人生設計と照らし合わせながら、後悔のない選択をするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。



